〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
受付時間
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)
遺言書作成
遺言書の種類

遺言書は、民法に定められた方式に従って作成しなければ、法的効力はありません。
遺言書の代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
|
方 式
| 遺言者が遺言の全文・作成日・氏名を自筆で書き、押印する。 ※なお、「財産目録」については、パソコンでの作成や、通帳コピー等の添付が認められるようになりました。(各ページに署名押印が必要) | 公証人が、二人以上の証人の立会いのもとに、遺言者が口授した内容を記載して作成する。 |
| メリット | ・一人で簡単に作成できる。 ・費用がかからない。 | ・公証人が作成するので、後日、裁判で無効とされる可能性が低い。 ・遺言の原本が公証役場に保管されるので、紛失の心配がない。 ・相続発生後に、家庭裁判所の検認の手続きがいらない。 |
| デメリット | ・形式の不備、内容の不明確で、遺言が無効になることがある。 ・むりやり書かされたのではないかと、後日紛争になる可能性あり。 ・紛失や隠匿の恐れがある。 ・相続発生後に、家庭裁判所の検認の手続きが必要である。 | ・費用と手間がかかる。 ・証人が二名以上、必要である。
|
※令和2年7月より、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まりました。
この制度を使うと、紛失や隠匿の恐れがなくなり、相続発生後の家庭裁判所の検認の手続きもいりません。
詳しくは、➡お役立ち情報「遺言書を法務局に預けて安心!」をご覧ください。
遺言書を作成しないと どうなるの?
遺言書がない場合、遺産は、相続人全員で行う遺産分割協議で分けることになります。
遺産分割協議をするには判断能力が必要で、相続人の一人が認知症になってしまったり、知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人がいる場合には、成年後見人等の選任が必要となります。
また、遺産に不動産があったりすると、その評価や、どう分けるかが問題となります。
相続人の中に、特別受益(生前贈与で住宅購入費用をもらった、など)や、寄与分(亡くなった方の財産の維持や増加に特別の貢献をしたこと)があったりすると、遺産分割協議で、もめたりします。
将来の紛争予防と安心ため、遺言書を作成しておくことが、大切です。
特に、注意しないといけないのが、「お子さんのいない ご夫婦」です。
「お子さんのいない ご夫婦」の場合、夫が亡くなった場合の相続人は、妻(持分4分の3)と夫の兄弟(持分4分の1)となります。(※ただし、すでに夫の両親や直系尊属が亡くなっている場合です)
「夫の兄弟は、妻が全部の遺産を取得することに同意してくれるだろう」と単純に考えるのは危険です。
遺産分割で3年にわたってもめたケースもあります。
夫が亡くなり、夫の兄弟も亡くなっていたので、夫の甥や姪が相続人となりました。
話合いが まとまらないため、妻が、甥や姪を相手に遺産分割調停を申し立てたのですが、その調停中に妻が亡くなり、妻の姪が調停を引継ぎました。
亡くなった夫は、自分の死後、まさかこんなことになるとは思っていなかったことでしょう。
夫が、遺言書を書いておきさえすれば、こんな争いにはならなかったのです。
また、紛争にならない場合でも、遺言書がないと、妻が相続手続きをするにあたっては、夫の兄弟の実印と印鑑証明書が必要となります。
「お子さんのいない ご夫婦」の場合、夫、妻、それぞれが遺言書を作成しておかれることをお勧めします。
全財産を妻に残したい場合の遺言書の書き方を、以下に載せておきます。
|
遺言者 鈴木一郎は、次の通り遺言する。
2.遺言執行者として、妻 鈴木花子を指定する。
令和〇年〇月〇日 ○○市○○区○○町〇丁目〇番〇号 遺言者 鈴木一郎 ㊞
|
|---|
遺言書を作成しておいた方が良い場合
- 夫婦の間に子どもがいない場合
- 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
- 相続人に、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人がいる場合
- 相続人に外国に居住している人がいる場合
- 長男の嫁にも遺産を分けてあげたい場合
- 相続人が全くいない場合
- 相続人に行方不明の人がいる場合
では、上記のような場合に、「遺言がない」とどうなるのでしょうか?
①夫婦の間に子どもがいない場合
配偶者と他の相続人との間で、遺産分割協議でもめる可能性がある。
②再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
遺産分割協議でもめる可能性が高い。
③相続人に、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人がいる場合
遺産分割協議をするために、成年後見人の選任が必要となる。
④相続人に外国に居住している人がいる場合
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書がないため、日本領事館等での手続きが必要となる。
⑤長男の嫁にも遺産を分けてあげたい場合
「長男の嫁」は相続人ではないため、遺言書で「遺贈する」と記載しない限り、遺産をもらえない。
介護などを無償で行ってきた親族が、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる制度が出来たが、「特別寄与料」の金額が合意できない場合、家庭裁判所への申立が必要となり、紛争となる。
⑥相続人が全くいない場合
利害関係人が相続財産管理人選任申立てを家庭裁判所に行い、債権申出の公告・相続人捜索の公告がなされ、特別縁故者への財産分与を経て、残った財産は国庫に帰属する。
⑦相続人に行方不明の人がいる場合
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ、無効。
行方不明者のために不在者財産管理人選任の申立を家庭裁判所に行い、不在者財産管理人と、他の相続人とで遺産分割協議を行う。
または、7年以上生死不明のときは、失踪宣告の申立を行い、死亡したとみなされた後に、他の相続人で遺産分割協議を行う。
遺言書作成の注意点
遺言書作成の注意点としては、各相続人の遺留分を侵害しない内容にしておくということです。
「遺留分」とは、相続人が最低限もらえる財産のことです。(なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。)
遺留分を侵害された相続人から請求があった場合、相続財産を多くもらった相続人等は、遺留分侵害額を金銭で支払わなければなりません。(2019年7月1日の法改正により、金銭での支払いと変更されました。)
遺言書作成の必要書類
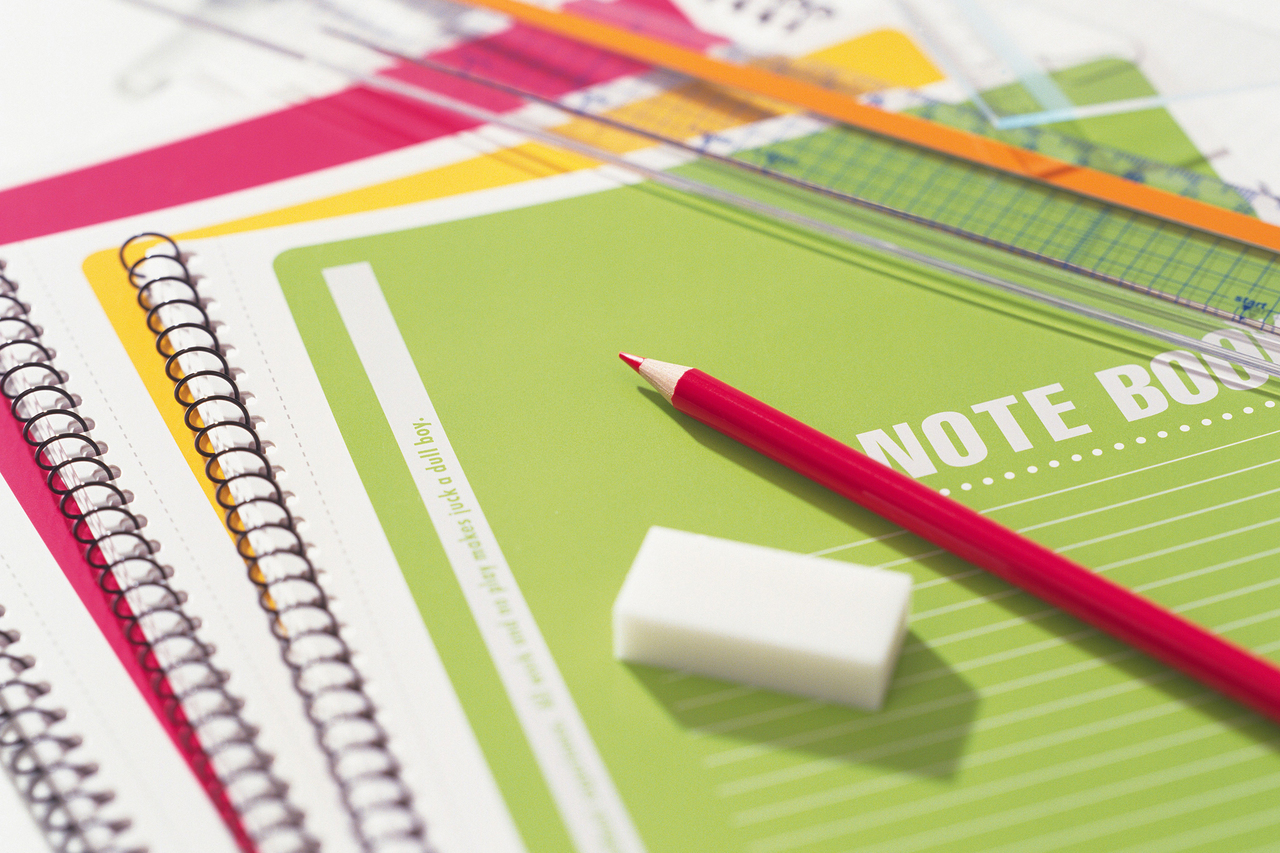
《 必要書類 》
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の住民票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 不動産の全部事項証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 金融資産の証明書類(残高証明書や預金通帳)
- 遺言者の印鑑証明書 及び 実印(公正証書遺言のとき)
自筆証書遺言作成サポートの費用
| 内容 | 司法書士報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 原案作成 | 55,000円 | 必要書類取得の実費 |
公正証書遺言作成サポートの費用
| 内容 | 司法書士報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 原案作成 | 77,000円 |
|
公証役場費用(公証人手数料令) 令和7年10月1日改正
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
※ 公証役場費用の留意点
1.財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
2.全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万3000円が加算(遺言加算)されます。
3.祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万3000円です。
4.遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
5.以上のほかに、証書の枚数による手数料の加算があります
遺言書作成の流れ
お問合せ

無料相談

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
お見積り・ご依頼
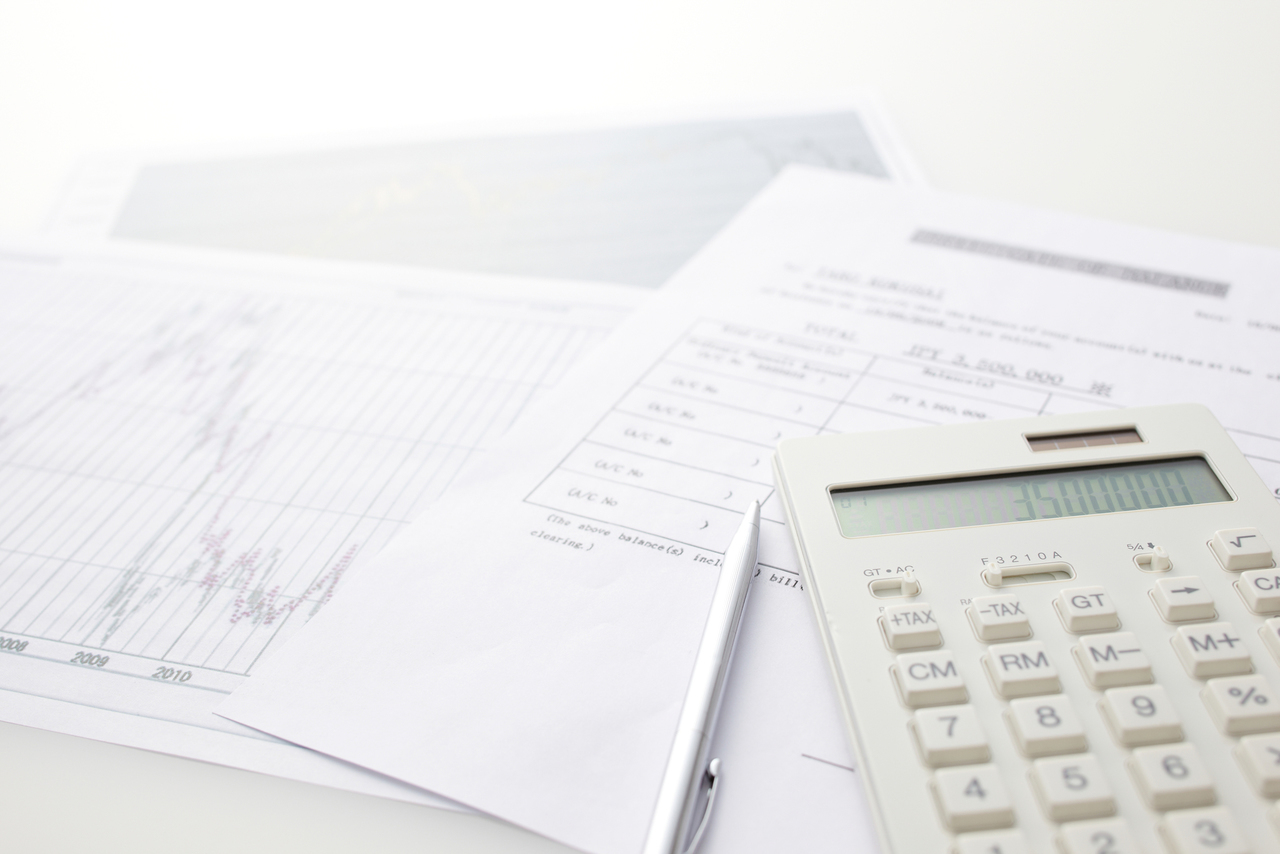
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。
業務開始

- 遺言内容の打合せ
- 必要書類の取得
- 遺言原案の作成
(公正証書遺言作成サポートの場合は、以下を含む)
- 公証役場との打合せ
- 公証役場で遺言書作成、証人1名立会い
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお、初回無料相談は対面のみとなっております。
あさい司法書士・行政書士
事務所

住所
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
アクセス
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/4番出口を出て南へ。クリーニング店とスーパー「とまと家族」さんの間を西へすぐ。ビストロOrangerieさんの2階/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)
新着情報・お知らせ
2026/1/18

