〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
受付時間
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)
成年後見制度
成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。
成年後見制度には、判断能力が不十分になってから申立てる「法定後見制度」と、判断能力がしっかりしているうちに準備する「任意後見制度」とがあります。
「法定後見制度」は、ご本人の判断能力の状況によって、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
| 対象となる方 | 援助者の名称・業務 | ||
|---|---|---|---|
| 法定後見 | 後見 | 判断能力が欠けている方 | 援助者:成年後見人 財産に関するすべての法律行為について、本人を代理する。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 援助者:保佐人 重要な財産に関する行為について、同意や取消を行う。 | |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 援助者:補助人 家庭裁判所が審判で定めた行為について、同意・取消・代理を行う。 | |
| 任意後見 | 援助者:任意後見人 本人の判断能力が不十分になった時に、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って、任意後見人が本人を代理する制度。 | ||
法定後見制度の利用方法
法定後見制度は、すでに判断能力が低下してしまった方の制度です。
成年後見制度(法定後見)を利用するには、まず、対象となる方(ご本人)の住所地の家庭裁判所に、申立てます。
申立てをすることが出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長等です。
家庭裁判所は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、成年後見人等を選任します。
申立時に、「成年後見人(保佐人・補助人)は、親族のこの人を選任してほしい」と希望を述べることはできますが、必ずしも希望通りに選任されるわけではありません。弁護士や司法書士や社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。
成年後見人(保佐人・補助人)は、毎年、家庭裁判所に業務報告をしなければなりません。
また、本人の財産の中から報酬を受け取ることができますが、その報酬額は、家庭裁判所がその業務の内容に応じて決定します。
一旦、成年後見制度の利用を始めると、本人の判断能力が回復するまで、または、本人がお亡くなりになるまで続きます。途中で中止することはできません。
任意後見制度の利用方法
任意後見制度は、判断能力が現在しっかりしている方の制度です。
ご本人が判断能力がしっかりしているうちに、「自分が将来、判断能力が不十分になった時には、この人にこういった業務をしてもらいたい」と、あらかじめ任意後見契約を公正証書で結んでおく制度です。
任意後見人の報酬なども、任意後見契約書の中で定めます。
法定後見だと、誰が成年後見人等に選任されるか、報酬はいくらか、は家庭裁判所が決定しますが、任意後見の場合は、本人が決定できます。
任意後見契約書に書いておけば、「長男が家を建てる時には、1000万円を贈与する」といった、法定後見では出来ないことも出来ます。
そして、将来、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行います。
申立てをすることが出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。
任意後見監督人が選任されることによって、任意後見が開始します。
任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが多いです。
任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定します。
成年後見サポートの料金表
| 内 容 | 報 酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 法定後見申立書作成 | 99,000円 | 裁判所費用約1万円+戸籍等の実費 (鑑定が行われる場合、5~10万円の鑑定費用がかかります。) |
| 任意後見各種契約書作成サポート (見守り契約書・財産管理契約書・任意後見契約書) | 220,000円(税込) | 公証役場費用+戸籍等の実費 |
| 任意後見監督人選任申立書作成 | 88,000円 (税込) | 裁判所費用約1万円+戸籍等の実費 |
※裁判所への面接に同行した場合、日当11,000円(税込)が加算となります。
法定後見サポートの流れ
(後見・保佐・補助)
お問合せ

無料相談

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
お見積り・ご依頼

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。
業務開始

お客様にご用意いただく書類をお伝えするとともに、当事務所で申立書等の必要書類を作成します。
- 申立書作成
- 申立事情説明書作成
- 親族関係図作成
- 財産目録作成
- 収支報告書作成
- 戸籍取得
- 住民票取得
書類が出来上がりましたら、申立人様の押印をいただきます。
家庭裁判所への申立て
家庭裁判所に面接予約を入れ、申立書を提出します。
家庭裁判所で申立人(可能であれば本人も)面接。所要時間は2時間程度です。
その後、調査がなされ、場合によっては裁判所の判断で鑑定が行われるケースもあります。
鑑定が行われると別途費用(5万円~10万円)がかかります。
調査等をふまえて、裁判所が後見(保佐・補助)開始の審判をし、申立人等に審判書が郵送されます。
(申立から審判まで、約1~2か月程度です。)
後見(保佐・補助)開始
申立人等が審判書を受領して2週間以内に不服申立てがなければ、審判が確定し、後見(保佐・補助)が開始します。
家庭裁判所から法務局に対し、成年後見の登記申請がされます。
任意後見サポートの流れ
お問合せ

無料相談

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
お見積り・ご依頼
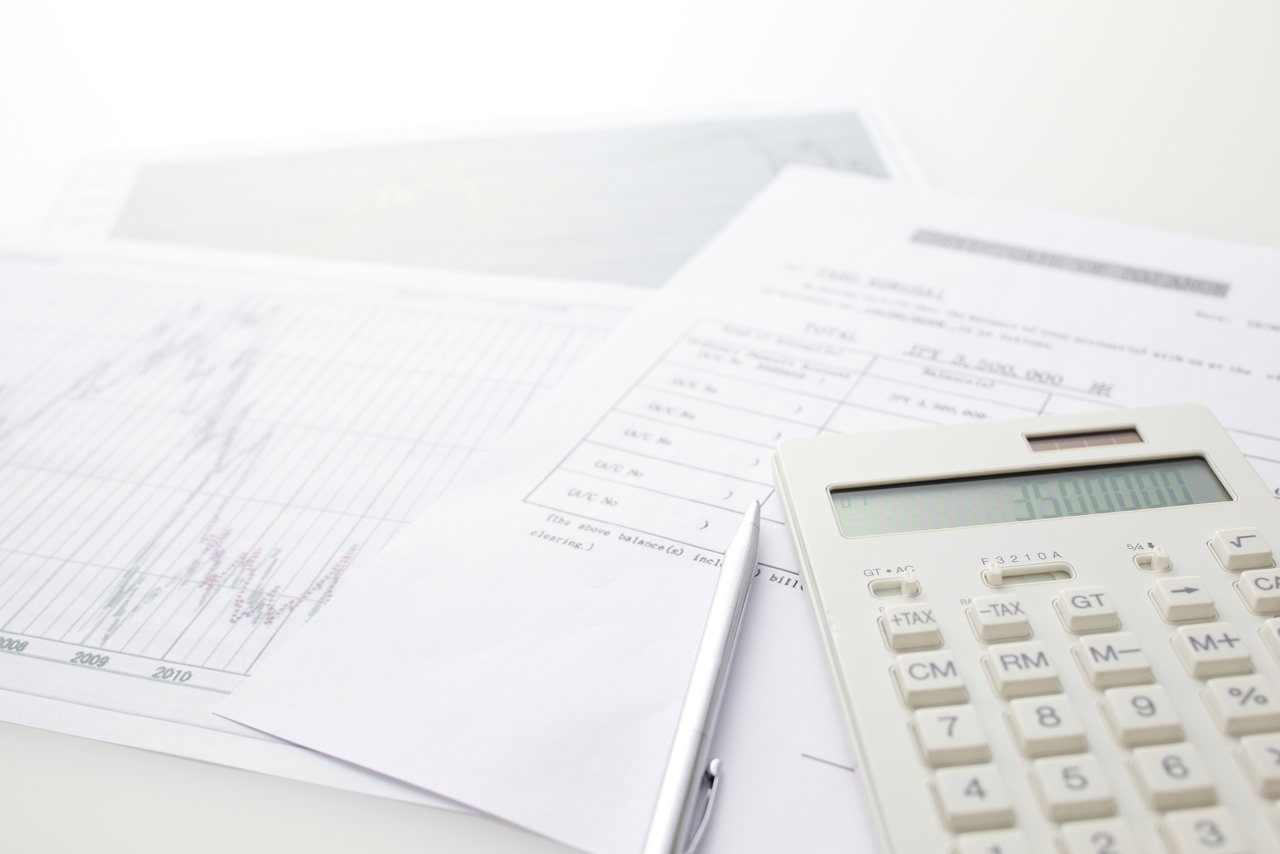
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。
業務開始

- ご本人の状況・ご希望等、丁寧にヒアリングします
- 各種契約書(案)の作成
- 公証人との打合せ
- 戸籍取得
- 住民票取得
公証役場で公正証書作成
本人と任意後見受任者が公証役場に行き、任意後見契約書などの公正証書を作成します。
公証人は、法務局に任意後見登記を行います。
これで、一旦終了です。
その後、ご本人の判断能力が低下した場合に、任意後見開始の手続きに移ります。
家庭裁判所へ申立て
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行います。
申立てをすることが出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。
家庭裁判所は、本人・任意後見受任者に面接をし、調査をふまえて、任意後見監督人の選任がされます。
任意後見監督人は、通常、弁護士や司法書士といった専門家が選任されます。
任意後見開始
家庭裁判所から、本人や任意後見受任者等に対し、任意後見監督人選任の通知がなされ、任意後見が開始します。
任意後見監督人選任については、2週間の不服申立期間はありません。関係者への告知によって効力が生じ、任意後見が開始されます。
家庭裁判所から法務局に対し、任意後見監督人の登記が申請されます。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお、初回無料相談は対面のみとなっております。
あさい司法書士・行政書士
事務所

住所
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
アクセス
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/4番出口を出て南へ。クリーニング店とスーパー「とまと家族」さんの間を西へすぐ。ビストロOrangerieさんの2階/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)
新着情報・お知らせ
2026/1/18

